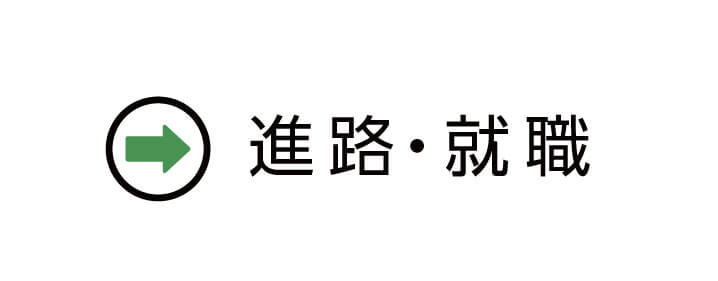北海学園学術情報リポジトリ HOKUGA 経済論集直近巻号のページへ
第73巻第2号(通巻第238号)
2025年11月
| 論説 |
日本林業の現在地と転換の起点―森林組合の意義と責務― |
| 著者 |
早尻 正宏 |
| 論説 |
今後の観光列車の在り方に関する一考察:JR 北海道の事例から見る「観光列車の上下分離試論」 |
| 著者 |
藤田 知也 |
| 論説 |
農福連携における生協・農協の役割:持続可能な社会への寄与 |
| 著者 |
畠山 明子 |
| 翻訳 |
「どのユダヤ人とも交渉したことはない。」―作家ルドヴィート・ミストリーク=オンドレヨフによるアーリア化― |
| 著者 |
ヤーン・フラヴィンカ 木村 和範(訳) |
| 翻訳 |
ユダヤ人の法的地位に関する1941年スロバキア共和国政令第198 号 |
| 著者 |
木村 和範(訳) |
第73巻第1号(通巻第237号)
2025年7月
| 論説 |
第一次資本自由化業種選定過程における通産省及び関係省庁の思想と動向 |
| 著者 |
板垣 暁 |
| 論説 |
イノベイティブ―企業理論の陥穽解読 William Lazonick and Jang-Sup-Shin (2020).―Predatory Value Extraction― |
| 著者 |
河西 勝 |
| 翻訳 |
日本の過長労働時間統計による正規雇用労働者の長時間労働問題への接近 |
| 著者 |
水野谷 武志 |
| 研究ノート |
広島市非正規公務員(会計年度任用職員)調査報告2 |
| 著者 |
川村 雅則 |
| 研究ノート |
北海道の小規模自治体における地域文化の創出過程に関する一考察―沼田町を事例に― |
| 著者 |
鈴木 健太 |
| 資料 |
手工業と大工業1880年2月21日ベルリン声楽協会でおこなわれた講演 |
| 著者 |
アードルフ・ヘルト (訳)太田 和宏 |
第72巻第3号(通巻第236号)
2025年3月
| 論説 |
17世紀中葉イングランドの雇用労働と奉公人:
ジョイス・ジェフリーズの家計簿から |
| 著者 |
石井 健 |
| 研究ノート |
韓国・平生教育士の職能団体の現状と課題(その1) |
| 著者 |
内田 和浩 |
| 研究ノート |
越谷市公契約条例に関する調査・研究(1) |
| 著者 |
川村 雅則 |
| 研究ノート |
世田谷区公契約条例に関する調査・研究(1) |
| 著者 |
川村 雅則 |
第72巻第2号(通巻第235号)
2024年11月
| 論説 |
『読売新聞』に見る自動車に対する論調の変化(3) 自動車の公害問題と論調の変化 |
| 著者 |
板垣 暁 |
| 論説 |
生活扶助相当CPI を用いたデフレ調整の始期に関する批判的検討 |
| 著者 |
鈴木 雄大 |
| 論説 |
原理論・段階論、そして脱資本主義分析 |
| 著者 |
河西 勝 |
第72巻第1号(通巻第234号)
2024年7月
| 論説 |
『読売新聞』に見る自動車に対する論調の変化(2) 自動車の事故・安全問題と論調の変化 |
| 著者 |
板垣 暁 |
| 論説 |
生活時間統計の国際比較方法 試行的な日独比較 |
| 著者 |
水野谷 武志 |
| 論説 |
JR 北海道の赤・黄線区の需要に関する一考察-需要関数の推計による分析 |
| 著者 |
藤田 知也 |
| 論説 |
半導体産業の政治経済学 新産業政策とその限界 |
| 著者 |
河西 勝・山本 哲三 |
| 研究ノート |
地域文化の理論的枠組みに関する一考察 持続可能な地域社会との関連で |
| 著者 |
鈴木 健太 |
第71巻第3号(通巻第232号)
2023年12月
| 論説 |
家畜市場における馬喰(家畜商)の活動実態に関する流通経済学的考察―北海道 森町の事例研究を中心として― |
| 著者 |
松浦 努 |
| 研究ノート |
旭川市非正規公務員(会計年度任用職員)調査報告―制度と労働条件の概要― |
| 著者 |
川村 雅則 |
| 翻訳 |
スロバキア国のプロパガンダにおける敵のイメージの諸類型 |
| 著者 |
エドゥアルド・ニジニャンスキー、カタリーナ・プシツォヴァ (訳)木村 和範 |
第71巻第2号(通巻第231号)
2023年9月
| 論説 |
非生活扶助相当品目の除外による「増幅」―生活扶助相当CPIに関する理論的・実証的検証― |
| 著者 |
鈴木 雄大 |
| 翻訳 |
1993年スロバキア共和国樹立後における歴史学と一般市民によるホロコーストの認識について |
| 著者 |
エドゥアルド・ニジニャンスキー、カタリーナ・ボホヴァ (訳)木村 和範 |
第71巻第1号(通巻第230号)
2023年6月
| 論説 |
小規模地域における地域文化の再生産のしくみ-北海道愛別町「あいべつ『きのこの里』フェスティバル」を事例として- |
| 著者 |
鈴木 健太 |
| 研究ノート |
札幌市非正規公務員(会計年度任用職員)調査報告―公募制と離職に関する情報の整理― |
| 著者 |
川村 雅則 |
| 翻訳 |
スロバキア内務省第14局長アントン・ヴァシェックと強制移送にたいするその責任 |
| 著者 |
ヴァンダ・ラジカン (訳)木村 和範 |
| 翻訳 |
テレジエンシュタットへのスロバキアからの強制移送―前史― |
| 著者 |
カタリーナ・フラツカ (訳)木村 和範 |
| 翻訳 |
ドイツ顧問官とスロバキアにおける「ユダヤ人問題の解決」 |
| 著者 |
カタリーナ・フラツカ (訳)木村 和範 |
第70巻第4号(通巻第229号)
2023年3月
| 論説 |
北海道・蘭越町における馬喰(家畜商)の活動実態に関する流通経済学的考察 |
| 著者 |
松浦 努 |
| 研究ノート |
ポリ塩化ビフェニール(PCB)処理をめぐる基本問題(4)―PCB汚染と放射能汚染の複合化― |
| 著者 |
小坂 直人 |
| 翻訳 |
韓国の平生教育の現場専門家-平生教育士を中心に- |
| 著者 |
内田 和浩 |
| 翻訳 |
マルクスと世界史 |
| 著者 |
ミヒャエル・R・クレトケ (訳)大屋 定晴 |
| 翻訳 |
大統領、スロバキア共和国政府、1942年におけるスロバキアからのユダヤ人強制移送 |
| 著者 |
マルティナ・フィアモヴァ (訳)木村 和範 |
| 翻訳 |
強制移送からユダヤ人を救おうとした「作業部会」 |
| 著者 |
カタリーナ・メシュコヴァ・フラツカ (訳)木村 和範 |
| 翻訳 |
悪魔の手先フリィッツ・フィアラ-書誌的研究試論- |
| 著者 |
ミハル・シュヴァルツ (訳)木村 和範 |
| 翻訳 |
スロバキア人とユダヤ人の協力と抵抗 |
| 著者 |
ハナ・クバートヴァ (訳)木村 和範 |
第70巻第3号(通巻第228号)
2022年12月
| 論説 |
地域経済を脆弱化させる国際事業活動の質的変化(Ⅱ)-ネオ・ラグマン流戦術転換理論の構築とその再釈義- |
| 著者 |
越後 修 |
| 論説 |
生計費測定指標としての生活扶助相当CPIの理論的問題点 |
| 著者 |
鈴木 雄大 |
| 翻訳 |
アウシュヴィッツの囚人医師 |
| 著者 |
ミクローシュ・ニスリ (訳)木村 和範 |